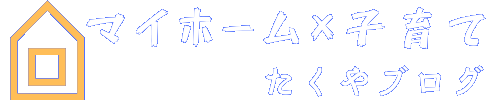子供が生まれる時、今住んでいる場所か里帰り出産で迷う人も多いのではないでしょうか?
居住地と実家が近ければ気軽に行き来できますが、実家が遠いと中々決断できませんよね。
我が家は散々迷ったあげく、里帰り出産をしなかったのですが、解決策はあってのことでした。
当時の状況は、3人家族で上の子(1歳半)で下の子(お腹の中)、妻の実家は最寄駅は車で1時間、僕の実家は自宅から30分程度でした。
これから出産を控えているママ、見守る立場になるパパ向けにお伝えしたいと思います。
まずは里帰り出産のメリット、デメリットを見ていきます。
里帰り出産のメリット

経験者である親がいる安心感
自分を育ててくれた親っていうだけで安心しますよね。
知り合いや友達ではなく、長年育ててくれた親なら些細なことでも気軽に相談もできます。
出産前はストレスが溜まりやすく情緒不安定になりやすいので、精神的な支えにもなります。
子供のことに専念できる
産前産後は安静にしておかないといけないと言います。
日中1人だと料理や洗濯などの家事を1人でやりながらというのは、体にも精神的にも負担がかかります。
その点、親が手伝ってくれるので無理をせず、大事な子供のことだけを考えられます。
里帰り出産のデメリット
一時的に夫婦別居状態
別居生活だけで関係が悪化する夫婦は「そんなもんか」と思ってしまうかもしれませんが、意外とすれ違いが発生してしまう危険性も秘めています。
中々連絡が取れないと色んな意味で心配になりますし、旦那さんが家事できないと・・・
世の中の旦那さんはきっと奥さんの手料理を食べたいと思っています。
親であるパパと中々対面できない
実家との距離にもよりますが、休日でないと旦那さんに自分の可愛い赤ちゃんを見せることができません。
僕がそうでしたが、日中も自分の子供に早く会いたくてたまりません。
写真で我慢!という案も出てきそうですが、やっぱり実物が見たいんですよね。
里帰り出産をしない場合は事前の準備で対策
うちは悩んだあげく、里帰り出産をしませんでした。
その代わりにあることを事前にしておくといざという時に安心できました。(妻の意見)
近くのタクシー会社の電話登録をしておく
いつ陣痛が来るかわかりません。
事前にタクシー会社の電話番号を登録しておくか、メモを取っておいて、いつでもすぐ迎えに来てもらえるようにします。
住所を言えば大体の場所はわかってもらえるはずですが、わかりづらい場所や新しい区画はナビでも出てこないケースがあります。
わかりやすい目印を伝えられるようにしておくと良いです。
万が一の場合も備えて複数タクシー会社を控えておくと満車で配車に時間がかかる、そもそも電話に繋がらないなんて緊急事態の確率を下げることができます。
計画出産
聞いた話によると、36週〜40週なら予め出産日を指定することもできるようです。
全ての産婦人科ではないかもしれませんが・・・
実際にうちは2人目の時、緊急事態を防ぐためにそうしました。
当然予定より早く産まれることもあるため、出産の準備は早いに越したことはありません。
早めに入院する
産婦人科によりますが、可能なら早めに入院するのもありです。
ただ入院したからといってすぐ出産できるかもわからないし、費用もかかるので他に手がないときに利用することになります。
旦那様、奥様とよく話し合い納得のいく決断を
旦那さんは奥さんと話し合い、望んでいる方を尊重することが大事。
これから大事な局面を迎える奥さんは里帰り出産をするかしないか早めの決断。
しないなら最小限のリスクになるようにしていただければと思います。
この記事が参考になれば幸いです。