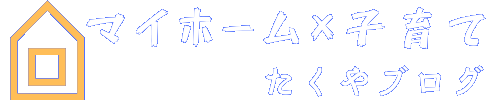毎日の通勤、通学で電車を利用している人は、都心を中心に多いと思います。
会社から支給されていることが多い定期券ですが、会社によって上限額が決まっていたり、そもそも給料に含まれているなんてことも。
定期券を一括で買う人もいれば、定期券を買わずに足りなくなってはチャージという二極化になると思います。
でも結局、何回の利用頻度で買った方が良いのか、買わない方が良いのか条件に応じて検証していきたいと思います。
今回は購入歴もある「つくばエクスプレス」、通称「TX」について書かせていただきます。
そもそもTXって運賃も定期券も他の路線に比べると高いですよね。(もっと安くしてくれば嬉しいのに・・・)
つくばエクスプレス(TX)の区間は?

つくばエクスプレスは、「秋葉原」から「つくば」までの20区間で成り立っています。
- 秋葉原(東京)
- 新御徒町(東京)
- 浅草(東京)
- 南千住(東京)
- 北千住(東京)
- 青井(東京)
- 六町(東京)
- 八潮(埼玉)
- 三郷中央(埼玉)
- 南流山(千葉)
- 流山セントラルパーク(千葉)
- 流山おおたかの森(千葉)
- 柏の葉キャンパス(千葉)
- 柏たなか(千葉)
- 守谷(茨城)
- みらい平(茨城)
- みどりの(茨城)
- 万博記念公園(茨城)
- 研究学園(茨城)
- つくば(茨城)
東京ー埼玉ー千葉ー茨城の一都三県を通る路線です。
一駅一駅算出しては複雑になってしまうので、下記2通りの条件にて算出しました。
- 始発終点である「つくば~秋葉原」
- 中間駅でもある「南流山から秋葉原」
余談ですが「つくばエキスプレス」と呼んでいる人がいますが、正式には違います。
「つくば」~「秋葉原」間比較
定期券なし
ICカード → 片道1,205円
切符 → 片道1,210円
往復時 → 1,205円×2回=2,410円(1日分)
※利用する人が多いICカードにて算出
定期券あり
1ヶ月 → 43,300円
43,300÷2,410=約17.97回
3ヶ月 → 123,410円(1ヶ月あたり約41,137円)
41,137÷2,410=約17.07回
6ヶ月 → 233,820円(1ヶ月あたり38,970円)
38,970÷2,410=約16.17回
南流山から秋葉原間比較
定期券なし
ICカード → 片道576円
切符 → 片道580円
往復時 → 576円×2回=1,152円(1日分)
※利用する人が多いICカードにて算出
定期券あり
1ヶ月 20,710円
20,710÷1,152=約17.98回
3ヶ月 59,030円(1ヶ月あたり19,677円)
19,677÷1,152=約17.08回
6ヶ月 111,840円(1ヶ月あたり18,640円)
18,640÷1,152=約16.18回
買った方がいい人と買わない方がいい人の境目
通勤においては、月に16回~18回程度利用する人が定期券を買うか、買わないかの境目だとわかりました。
つまり、週5以上で毎日同じ通勤ルートの場合は定期券を購入した方が安くなります。
しかし、出張が多い人やシフト制で出勤日数がバラバラという人は、買わない方が結果的に安くなる可能性が高いです。
会社によっては、定期券をちゃんと購入しているかチェックしているところもあるので、そこは会社のルールに従ってください。
ちなみに、僕のところは定期券代分支給されますが、購入するかは自由と言われています。
定期代の支給が開始日より後の場合は現金がなく、高額になる定期代が払えないという場合を除き、まとめ買いが安くなります。
尚、有人定期券券売所は秋葉原、北千住、守谷、つくばの4ヶ所で定期券発行機能付自動券売機は全駅で購入可能です。
定期券を購入するならいつが良い?
期の変わり目が一番混むので避けた方が良いです。
- 3月27日~4月3日
- 9月27日~10月3日
このあたりは定期券を購入する人たちで券売機、特に窓口は激混みです。
僕もドはまりで、30分以上待ったことがあります。
定期券を買うだけなのに長蛇の列に!
なので、期の変わり目は避けて余裕を持って購入すると、無駄な時間を作らなくて済みます。
継続で購入⇒14日前から
もちろん料金も購入した日付からではなく、指定した日付から使用開始、及び料金が発生します。
どうしても激混みの日にしかいけない場合は、朝と夕方の通勤時間帯は避けるべき。
午前中であれば9時半~11時半くらい、午後であれば14時~17時くらいだと比較的空いています。
ご参考にしていただけたら幸いです。
毎日の通勤、通学で電車を利用している人は都心を中心に多いと思います。会社から支給されていることが多い定期券ですが、会社によって上限額が決まっていたり、そもそも給料に含まれているなんてことも聞きます。定期券を一括で買う人もいれ[…]
前回は「JR常磐線の通勤定期券」について比較しました。今回は学生向けの通学定期券について比較していきたいと思います。切符、もしくはICカードで足りなくなってはチャージのパターンと定期券を購入するパターンの二極化。結局[…]